朝からシトシトと雨降りの秋田。それでも気温が高いのか、雪解けがさらに進んでいます。山からの帰り道、道路と田んぼの間に流れている小川には、水が流れ、長い冬の間雪に埋もれていた姿を現しました。下の写真左側、積雪に絶えかねて途中から折れたポールと小川、そして崩れかかった雪のアーチ。中央はいつだったか、登場してくれた「羊」が顔を出していました(「2005.12.22
今年のセミナー日程終了」)。
上の写真右側は、収穫したバッケ(フキノトウ)と、みそ、それにクルミをフードプロセッサーですりつぶしているところ。下の写真左側は、完成したバッケみそ(フキノトウのみそあえ)。
ばっぱは朝から、あんこを丸めて皿にもっていました。何を作るとかと見ていると、餅米を炊いて、それをすりこぎでつぶしたモチの中に入れて、平べったく形を整え、きな粉をまぶした「なべすりモチ」を作っていたのでした(下の写真中央、右)。
少しさめてから、さらに形を整えてできあがり(下写真中央)。夕食のお料理は、イカ、セロリ、マッシュルームの炒めもの(下写真右)。塩とコショウ、それにお酒で炒めたモノで、イカの味がセロリのほろ苦い味にかわり、バッケみそとの相性、抜群のお料理でした。
新聞に「肺ガン発見より早く - 広がるCT検診」なる見出しが。内容を見ていくと、ポイントは、
・ガンで亡くなられる方のうち、肺ガンがとても多い
・エックス線撮影により、早期発見することができるも、限界がある
・現代ではマルチスライスCTによって、ガンとして疑わしい部位を早期発見可能
・ただし、肺ガンの早期発見によるメリットと、検診による被爆というデメリットが伴う
・そのメリットは、50歳以上
というものでした。
従来のエックス線撮影では、平面的な情報をもとに、医師の長年の経験と判断で肺ガンの早期発見が可能でしたが、CTによる検診では、0.625ミリ間隔で、513枚もの断面画像が得られ、それを画像処理して、立体的に見ることができるまでになっているそうです(「2005.12.20 ペットとルアーの組み合わせ」)。
二、三日前、アップルからメールが届きました。その中で、「アップル - Medical - OsiriXがもたらす医用画像利用環境の変革」という内容が目につきましたが、ハードやソフトの面でもその画像処理能力は飛躍的に進歩しているようです。
結果的には、今まで見落としていた病巣までも見落とすことなく、早期発見が可能となりましたが、一方では、その検診に利用する CT からの被爆の問題があります。当初は、集団検診で一般的に用いられるエックス線による撮影から受ける被爆量の 10倍もの有害光線を受けていたそうです。現在では、ほぼ同レベルの 0.35ミリシーベルトというレベルまで減少したそうですが、被爆という意味では、人体にとってはデメリットです。
しかし、肺ガン(ガン)が、もしも発見できないで、人体に与えるデメリットを考えると、どちらがメリット、デメリットかという問題がでてきます。何でも、被爆のリスクは、50歳以上なら、CT検診よる利益の方が、被爆のデメリットを上回るという試算がはじき出されているようです。
そのようなメリット、デメリットを考えて意思決定を支えるものに、損益分岐点という会計の用語があります。
簡単なモデルで、説明(するまでもないか)するとすれば、売上げから、経費を引いた残りが「利益」としてとらえられていますが、このような考え方を「財務会計的」というそうです。そうではなく、目標の利益はこれだけ欲しい、そのためにどれだけの売上げを達成しないといけないのか。このような考え方を「管理会計的」といっていたはずです。
その管理会計的発想の要に、損益分岐点なる考え方があります。これは、サロンをされている方、商品を販売されている方にとても役に立つ考え方です。
通常の経費を、変動費と固定費という概念に分解します。固定費は何となくおわかりの通り、売上げがなくても、月に必ず発生する費用のこと。一番いい例として家賃や、水道光熱費(ちょっとは変動するかもしれませんが)など。
そして、変動費は、売上げと相関関係のある費用。一番わかりやすいのが商品の仕入れにより発生した費用(売上原価といいます)です。一定の掛け率により、商品が仕入れられますから、売上げがいくらあっても、その売上げの一定比率は常に、仕入のための費用となります。
さあ、そこで、売上げから変動費を差し引いた残りの金額で固定費を支払うわけですから、差し引いた残りの金額が、固定費よりも大きければ「利益」となります。また、その逆で、差し引いた残りの金額が、固定よりも少なければ「損失」となります。
ここで、問題です。差し引いた残りの金額と固定費の金額が一緒の場合はどうなるでしょうか。
簡単ですよね、そう、プラスマイナス「ゼロ」になります。このゼロになるということは、差し引いた残りの金額と固定費の金額が一緒の場合でしたよね。ということは、差し引いた残りの金額って、売上げから変動費を差し引いた金額でしたので、その差し引いた金額を得ることのできる売上高が求められます。その売上げを「損益分岐点」といいます(正確には損益分岐点における売上高)。
ここで、下記の図をご覧下さい。
上の図での、損益分岐点における売上高は、5,000円となりますよね。どうしてかっていうと、売上げの 5,000円の 60%が変動費ですから、5,000円マイナス3,000円(5,000円かける60%)、これが差し引きの金額で、2,000円です。この差し引き金額のことを、専門的には「限界利益」といいます。
さあ、この2,000円で、売上げがあってもなくても発生する固定費 2,000円を支払わなくてはなりません。差し引きすると、ゼロになりました。利益がゼロになる売上高が損益分岐点となる売上げ 5,000円でした。
表に現すともっとわかりやすくなります(上の右側の表)。どうですか、売上げ 5,000円を超えると利益がでてくるし、5,000円を下回ると損失がでてきます。その関係をこの表は現しています。
ちょっと、関係の薄い話をしましたが、何か、被爆のリスクって、この損益分岐点の表に似ていると思いませんか。
精油の中には、放射線防護作用を持っているものがあります。これは、放射線による皮膚の損傷を防護するために利用されるようですが、免疫系とも関係のある精油の仲間ですよね。
その精油は、
・ティートゥリー Melaleuca alternifolia
・ニアウリ CT1 Melaleuca quinquenervia CT1 (Cineole)
といわれています。ひまわりも、CT検診を受けるちょうど損益分岐点年齢の 50歳、でも、一番大切なのは、そうならないような、交感神経緊張の状態を早く脱することですよね。そうすると、損益分岐点年齢は、下がるわけですから。それって、売上げが多いの、それとも変動費が少ないの、あるいは固定費が少ないからなの?。体のことを、この考え方に置きかえるとおもしろいかもしれません。
すべて条件ということに落ち着きそうですね。それは、個体差による植物療法(フィトテラピー)です。ここでも、結構メリットとデメリットのせめぎ合いがあります。
 |
 |
 |
上の写真右側は、収穫したバッケ(フキノトウ)と、みそ、それにクルミをフードプロセッサーですりつぶしているところ。下の写真左側は、完成したバッケみそ(フキノトウのみそあえ)。
ばっぱは朝から、あんこを丸めて皿にもっていました。何を作るとかと見ていると、餅米を炊いて、それをすりこぎでつぶしたモチの中に入れて、平べったく形を整え、きな粉をまぶした「なべすりモチ」を作っていたのでした(下の写真中央、右)。
 |
 |
 |
少しさめてから、さらに形を整えてできあがり(下写真中央)。夕食のお料理は、イカ、セロリ、マッシュルームの炒めもの(下写真右)。塩とコショウ、それにお酒で炒めたモノで、イカの味がセロリのほろ苦い味にかわり、バッケみそとの相性、抜群のお料理でした。
 |
 |
 |
新聞に「肺ガン発見より早く - 広がるCT検診」なる見出しが。内容を見ていくと、ポイントは、
・ガンで亡くなられる方のうち、肺ガンがとても多い
・エックス線撮影により、早期発見することができるも、限界がある
・現代ではマルチスライスCTによって、ガンとして疑わしい部位を早期発見可能
・ただし、肺ガンの早期発見によるメリットと、検診による被爆というデメリットが伴う
・そのメリットは、50歳以上
というものでした。
従来のエックス線撮影では、平面的な情報をもとに、医師の長年の経験と判断で肺ガンの早期発見が可能でしたが、CTによる検診では、0.625ミリ間隔で、513枚もの断面画像が得られ、それを画像処理して、立体的に見ることができるまでになっているそうです(「2005.12.20 ペットとルアーの組み合わせ」)。
二、三日前、アップルからメールが届きました。その中で、「アップル - Medical - OsiriXがもたらす医用画像利用環境の変革」という内容が目につきましたが、ハードやソフトの面でもその画像処理能力は飛躍的に進歩しているようです。
結果的には、今まで見落としていた病巣までも見落とすことなく、早期発見が可能となりましたが、一方では、その検診に利用する CT からの被爆の問題があります。当初は、集団検診で一般的に用いられるエックス線による撮影から受ける被爆量の 10倍もの有害光線を受けていたそうです。現在では、ほぼ同レベルの 0.35ミリシーベルトというレベルまで減少したそうですが、被爆という意味では、人体にとってはデメリットです。
しかし、肺ガン(ガン)が、もしも発見できないで、人体に与えるデメリットを考えると、どちらがメリット、デメリットかという問題がでてきます。何でも、被爆のリスクは、50歳以上なら、CT検診よる利益の方が、被爆のデメリットを上回るという試算がはじき出されているようです。
そのようなメリット、デメリットを考えて意思決定を支えるものに、損益分岐点という会計の用語があります。
簡単なモデルで、説明(するまでもないか)するとすれば、売上げから、経費を引いた残りが「利益」としてとらえられていますが、このような考え方を「財務会計的」というそうです。そうではなく、目標の利益はこれだけ欲しい、そのためにどれだけの売上げを達成しないといけないのか。このような考え方を「管理会計的」といっていたはずです。
その管理会計的発想の要に、損益分岐点なる考え方があります。これは、サロンをされている方、商品を販売されている方にとても役に立つ考え方です。
通常の経費を、変動費と固定費という概念に分解します。固定費は何となくおわかりの通り、売上げがなくても、月に必ず発生する費用のこと。一番いい例として家賃や、水道光熱費(ちょっとは変動するかもしれませんが)など。
そして、変動費は、売上げと相関関係のある費用。一番わかりやすいのが商品の仕入れにより発生した費用(売上原価といいます)です。一定の掛け率により、商品が仕入れられますから、売上げがいくらあっても、その売上げの一定比率は常に、仕入のための費用となります。
さあ、そこで、売上げから変動費を差し引いた残りの金額で固定費を支払うわけですから、差し引いた残りの金額が、固定費よりも大きければ「利益」となります。また、その逆で、差し引いた残りの金額が、固定よりも少なければ「損失」となります。
ここで、問題です。差し引いた残りの金額と固定費の金額が一緒の場合はどうなるでしょうか。
簡単ですよね、そう、プラスマイナス「ゼロ」になります。このゼロになるということは、差し引いた残りの金額と固定費の金額が一緒の場合でしたよね。ということは、差し引いた残りの金額って、売上げから変動費を差し引いた金額でしたので、その差し引いた金額を得ることのできる売上高が求められます。その売上げを「損益分岐点」といいます(正確には損益分岐点における売上高)。
ここで、下記の図をご覧下さい。
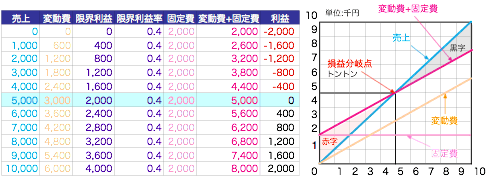 |
上の図での、損益分岐点における売上高は、5,000円となりますよね。どうしてかっていうと、売上げの 5,000円の 60%が変動費ですから、5,000円マイナス3,000円(5,000円かける60%)、これが差し引きの金額で、2,000円です。この差し引き金額のことを、専門的には「限界利益」といいます。
さあ、この2,000円で、売上げがあってもなくても発生する固定費 2,000円を支払わなくてはなりません。差し引きすると、ゼロになりました。利益がゼロになる売上高が損益分岐点となる売上げ 5,000円でした。
表に現すともっとわかりやすくなります(上の右側の表)。どうですか、売上げ 5,000円を超えると利益がでてくるし、5,000円を下回ると損失がでてきます。その関係をこの表は現しています。
ちょっと、関係の薄い話をしましたが、何か、被爆のリスクって、この損益分岐点の表に似ていると思いませんか。
精油の中には、放射線防護作用を持っているものがあります。これは、放射線による皮膚の損傷を防護するために利用されるようですが、免疫系とも関係のある精油の仲間ですよね。
その精油は、
・ティートゥリー Melaleuca alternifolia
・ニアウリ CT1 Melaleuca quinquenervia CT1 (Cineole)
といわれています。ひまわりも、CT検診を受けるちょうど損益分岐点年齢の 50歳、でも、一番大切なのは、そうならないような、交感神経緊張の状態を早く脱することですよね。そうすると、損益分岐点年齢は、下がるわけですから。それって、売上げが多いの、それとも変動費が少ないの、あるいは固定費が少ないからなの?。体のことを、この考え方に置きかえるとおもしろいかもしれません。
すべて条件ということに落ち着きそうですね。それは、個体差による植物療法(フィトテラピー)です。ここでも、結構メリットとデメリットのせめぎ合いがあります。